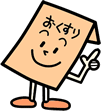インフルエンザ
和歌山市の今シーズン(2025-26年)の流行状況について
例年より早く11月中旬にかけて急増しました。その後、減少傾向にありましたが、1月下旬に再び急増しています。
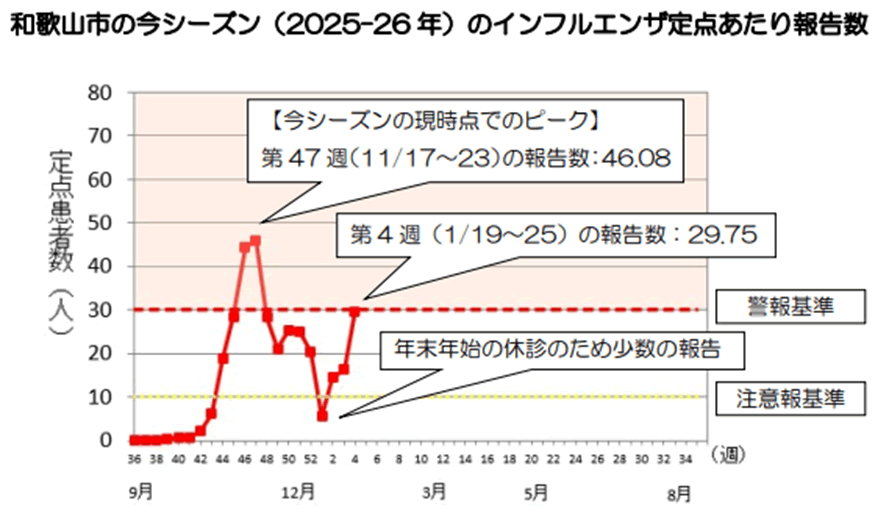
学校からの出席停止や学級閉鎖の報告も増加しており、今後さらに流行が拡大する可能性があります。
各家庭や施設・学校等の集団生活においては、手洗いや咳エチケットなどの感染対策を徹底しましょう。
また、重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患をお持ちの方等)は、早めに医療期間を受診しましょう。
例年より早く11月中旬にかけて急増しました。その後、減少傾向にありましたが、1月下旬に再び急増しています。
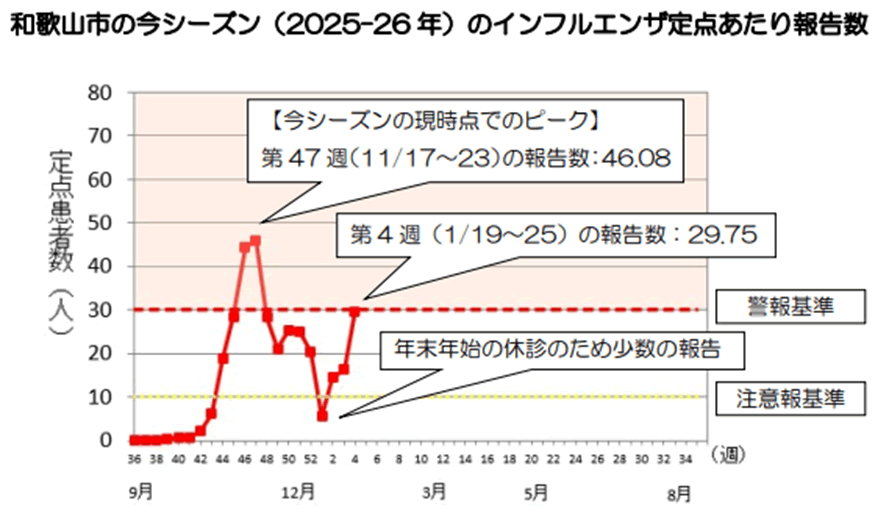
学校からの出席停止や学級閉鎖の報告も増加しており、今後さらに流行が拡大する可能性があります。
各家庭や施設・学校等の集団生活においては、手洗いや咳エチケットなどの感染対策を徹底しましょう。
また、重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患をお持ちの方等)は、早めに医療期間を受診しましょう。

インフルエンザを正しく知りましょう
インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染による感染症で、普通の風邪とは異なり、呼吸器症状や38℃以上の発熱、頭痛、関節痛等の全身症状等が現れます。健康な成人では、発熱が2~3日持続した後、1週間程度で回復しますが、お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を併発する等、重症になることがあり、注意が必要です。
感染を広げないために、医療機関受診時の適切な行動、感染した人が他の人に感染させない配慮など、感染症から身を守るために、正しい情報をしっかり持ち、適切な予防と行動をすることが大切です。 インフルエンザウイルス インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、A型、B型、C型に大きく分類され、このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。A型には、多数の種類があります。
感染を広げないために、医療機関受診時の適切な行動、感染した人が他の人に感染させない配慮など、感染症から身を守るために、正しい情報をしっかり持ち、適切な予防と行動をすることが大切です。 インフルエンザウイルス インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、A型、B型、C型に大きく分類され、このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。A型には、多数の種類があります。
A/H1N1:かつてはソ連と呼ばれているものが流行していましたが、新たに2009年発生した型が置き換わって流行しています。
A/H3N2:香港型と呼ばれており、1968年から流行しています。
B型:A型と症状も似ており、予防対策も同じです。
インフルエンザウイルスは変異しやすいウイルスであり、今後、より病原性の高い新型インフルエンザが発生した場合に備えての準備も重要となります。

インフルエンザって?どんな症状?どんな感染?
症状
インフルエンザは、38℃以上の発熱や咳、のどの痛み、全身の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状が突然現れます。
ハイリスク者(重症化しやすい人)
・お年寄り
・お子さん
・妊婦さん
・次の持病がある方:慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、慢性心疾患、糖尿病
→持病のある方は主治医にご相談ください。主治医と相談してできるだけ予防接種を受けましょう。 流行の時期 その年により流行に差はありますが、通常11月下旬から12月上旬に始まり、翌年の1~3月ごろに患者数が増加します。いったん流行が始まると、短時間に多くの人へ感染が広がります。 感染経路 インフルエンザウイルスが人の体内に入りこむことで感染します。主な経路は、飛沫感染と接触感染が考えられます。 飛沫感染 感染した人の咳、くしゃみ、つばなどとともに放出されたウイルスを吸い込むことで感染します。通常2mぐらい離れると感染することはないと考えられていますので、症状があれば「咳エチケット」の徹底をお願いします。 接触感染 感染した人のつばやくしゃみのかかった場所にさわった手で口や鼻、目の粘膜にふれることででも感染が拡がるとも考えられます。 感染予防のため、適切な手洗いが必要です。
・お子さん
・妊婦さん
・次の持病がある方:慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、慢性心疾患、糖尿病
→持病のある方は主治医にご相談ください。主治医と相談してできるだけ予防接種を受けましょう。 流行の時期 その年により流行に差はありますが、通常11月下旬から12月上旬に始まり、翌年の1~3月ごろに患者数が増加します。いったん流行が始まると、短時間に多くの人へ感染が広がります。 感染経路 インフルエンザウイルスが人の体内に入りこむことで感染します。主な経路は、飛沫感染と接触感染が考えられます。 飛沫感染 感染した人の咳、くしゃみ、つばなどとともに放出されたウイルスを吸い込むことで感染します。通常2mぐらい離れると感染することはないと考えられていますので、症状があれば「咳エチケット」の徹底をお願いします。 接触感染 感染した人のつばやくしゃみのかかった場所にさわった手で口や鼻、目の粘膜にふれることででも感染が拡がるとも考えられます。 感染予防のため、適切な手洗いが必要です。

インフルエンザかもしれない?と思ったら
電話で相談!マスクで受診!
・和歌山県救急医療情報センター(24時間対応) TEL(073)426-1199
- 事前に「かかりつけ医師」など医療機関に電話をして指示を受けましょう。
- 受診時は、必ずマスクを着用しましょう。
- 妊娠している方や人工透析を受けているなど慢性疾患の方はあらかじめ、かかりつけ医師に相談しておきましょう。
・和歌山県救急医療情報センター(24時間対応) TEL(073)426-1199

インフルエンザにかかったら!
一般的な注意
こんな症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
インフルエンザ脳症についてインフルエンザ脳症は主に5歳以下の乳幼児に発症し、インフルエンザ発病後の急速な病状の進行と予後の悪さを特徴とする疾患です。
インフルエンザ脳症の早期の症状は、インフルエンザ様症状(発熱等)に加え、
薬の使用にあたっての注意点インフルエンザの治療に用いられる薬としては、抗インフルエンザウイルス薬があります。これは、医師が患者それぞれの状態に応じ、判断して処方されます。
その他、インフルエンザウイルスには直接効果はありませんが、解熱剤やインフルエンザに合併する肺炎や気管支炎に対する治療として抗生物質等が使用されることがあります。
それぞれの薬の効果は、ひとりひとりの症状や体調によっても異なり、正しい飲み方、副作用への注意などがありますので、次のことを守って薬を使用してください。
特に、解熱剤については、主に15歳未満の方がインフルエンザの時に使用する場合、注意を要するものがあります(ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸等)。インフルエンザのとき、自己判断での解熱剤の服用はやめましょう。
なお、いわゆる「かぜ薬」と言われるものは、発熱や鼻汁、鼻づまりなどの症状を和らげることはできますが、インフルエンザウイルスに直接効くものではありません。
小児・未成年者の異常行動に注意!! 抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、インフルエンザと診断され治療が開始された後、少なくとも2日間は、保護者等は小児・未成年者が一人にならないように配慮して下さい。 異常行動が発生した場合でも、小児・未成年者が容易に住居外に飛び出さないための対策としては以下のような対策が考えられます。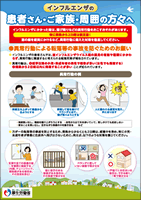 <異常行動の例>
<異常行動の例>
- 医療機関に電話連絡し受診についてアドバイスを受けましょう。
- 安静にして、できるだけ休養を取りましょう。特に睡眠を十分取ることが大切です。
- 水分を十分に補給しましょう。お茶、ジュース、スープなど飲みたいもので結構です。
- インフルエンザは感染しやすいので、マスクを着用し、また、無理をして職場などに行かないようにしましょう。
- 熱が下がっても、約2日間はウイルスは排出されているといわれています。
- 学校や会社等の感染対策方針に従い、必要に応じて、自宅療養につとめましょう。
| こども | おとな |
|
|
こんな症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
インフルエンザ脳症についてインフルエンザ脳症は主に5歳以下の乳幼児に発症し、インフルエンザ発病後の急速な病状の進行と予後の悪さを特徴とする疾患です。
インフルエンザ脳症の早期の症状は、インフルエンザ様症状(発熱等)に加え、
- 呼びかけに答えないなど意識レベルの低下が見られる
- けいれん重積およびけいれん後の意識障害が持続する
- 意味不明の言動が見られる
薬の使用にあたっての注意点インフルエンザの治療に用いられる薬としては、抗インフルエンザウイルス薬があります。これは、医師が患者それぞれの状態に応じ、判断して処方されます。
抗インフルエンザウイルス薬 |
|
それぞれの薬の効果は、ひとりひとりの症状や体調によっても異なり、正しい飲み方、副作用への注意などがありますので、次のことを守って薬を使用してください。
- 医師が患者本人に処方した薬を用法・用量・服薬期間を守って服用してください。
- 他の人に処方された薬はもちろん、本人用のものであっても、別の病気のために処方されて使い残したものを使用することは避けてください。
- 処方された薬については、医療機関、薬局などできちんと説明を受けてください。
特に、解熱剤については、主に15歳未満の方がインフルエンザの時に使用する場合、注意を要するものがあります(ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸等)。インフルエンザのとき、自己判断での解熱剤の服用はやめましょう。
なお、いわゆる「かぜ薬」と言われるものは、発熱や鼻汁、鼻づまりなどの症状を和らげることはできますが、インフルエンザウイルスに直接効くものではありません。
小児・未成年者の異常行動に注意!! 抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、インフルエンザと診断され治療が開始された後、少なくとも2日間は、保護者等は小児・未成年者が一人にならないように配慮して下さい。 異常行動が発生した場合でも、小児・未成年者が容易に住居外に飛び出さないための対策としては以下のような対策が考えられます。
異常行動による事故を防ぐためには・・
(1)高層階の住居の場合
・ 玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う(内鍵、補助錠がある場合はその活用を含む。)
・ ベランダに面していない部屋で寝かせる
・ 窓に格子のある部屋で寝かせる(窓に格子がある部屋がある場合)
(2) 一戸建ての場合
・(1)に加え、出来る限り1階で寝かせる
(1)高層階の住居の場合
・ 玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う(内鍵、補助錠がある場合はその活用を含む。)
・ ベランダに面していない部屋で寝かせる
・ 窓に格子のある部屋で寝かせる(窓に格子がある部屋がある場合)
(2) 一戸建ての場合
・(1)に加え、出来る限り1階で寝かせる
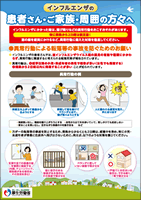 <異常行動の例>
<異常行動の例>- 突然立ち上がって部屋から出ようとする
- 興奮状態となり、手を広げて部屋を駆け回り、意味のわからないことを言う
- 興奮して窓を開けてベランダに出ようとする
- 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
- 人に襲われる感覚を覚え、外に飛び出す
- 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る
- 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする

インフルエンザにかからないために!
インフルエンザを予防する方法としては、以下が挙げられます。
外出後の手洗い等手洗いは手指など体に付着したインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず感染予防の基本です。
また、外出後の手洗い、うがいは一般的な感染症の予防のためにもおすすめします。
正しい手洗い方法 咳エチケットを守りましょう咳・くしゃみが出たらマスクを着けましょう。 咳エチケット 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取体の抵抗力を高めるために、十分な栄養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。
人混みや繁華街への外出を控えるインフルエンザが流行してきたら、特にご高齢の方や慢性疾患をお持ちの方、疲労気味、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。やむを得ず外出をして人混みに入る可能性がある場合、不織布(ふしょくふ)製マスクを着用することは、ある程度の飛沫等を捕捉できるため、ひとつの防御策と考えられます。ただし、人混みに入る時間は極力短時間にしましょう。
外出後の手洗い等手洗いは手指など体に付着したインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず感染予防の基本です。
また、外出後の手洗い、うがいは一般的な感染症の予防のためにもおすすめします。
正しい手洗い方法 咳エチケットを守りましょう咳・くしゃみが出たらマスクを着けましょう。 咳エチケット 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取体の抵抗力を高めるために、十分な栄養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。
人混みや繁華街への外出を控えるインフルエンザが流行してきたら、特にご高齢の方や慢性疾患をお持ちの方、疲労気味、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。やむを得ず外出をして人混みに入る可能性がある場合、不織布(ふしょくふ)製マスクを着用することは、ある程度の飛沫等を捕捉できるため、ひとつの防御策と考えられます。ただし、人混みに入る時間は極力短時間にしましょう。
※不織布製マスクとは?
不織布とは「織っていない布」という意味です。ガーゼマスクのように繊維あるいは糸等を織ったりせず、熱や化学的な作用によって接着させて布にしたもので、さまざまな用途で用いられています。市販されている家庭用マスクの約97%が不織布製マスクです。
流行前のワクチン接種インフルエンザワクチンは、かかった場合の重症化予防に有効と報告されています。 65歳以上の方の定期予防接種はこちら
不織布とは「織っていない布」という意味です。ガーゼマスクのように繊維あるいは糸等を織ったりせず、熱や化学的な作用によって接着させて布にしたもので、さまざまな用途で用いられています。市販されている家庭用マスクの約97%が不織布製マスクです。

その他の情報